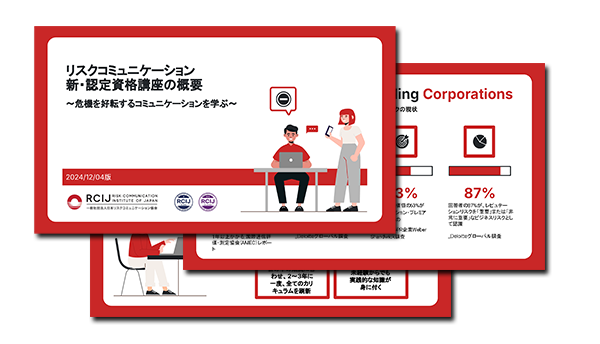ESG投資家との”対話”が企業価値に影響──スチュワードシップ・コード改訂(金融庁)
2025.08.15
2025年6月、金融庁が「スチュワードシップ・コード」の第三次改訂版を発表しました。
この記事では、企業のコミュニケーション戦略に関わる皆さんが押さえるべきポイントを解説します。
Contents
スチュワードシップ・コードって何?
スチュワードシップ・コードとは、企業に投資する機関投資家が「責任ある投資家」として、投資先企業との建設的な対話(エンゲージメント)を通じて、企業価値の向上と持続的成長を促すための行動指針です。いわば、企業と投資家が“共同で会社を良くしていくための対話ルール”ともいえるでしょう。
スチュワードシップ・コードは、細かいルールを設ける“ルールベース”ではなく、各機関投資家が自らの立場に応じて「原則(プリンシプル)」に則った行動をとる“プリンシプルベース・アプローチ”を採用しています。これは、形式的な遵守よりも、行動の背景や意図を説明できる「納得性のあるコミュニケーション」が求められているということです。
たとえば、原則通りの開示をしていない場合でも、それには理由があるなら「エクスプレイン(説明)」すればいい、というのが「コンプライ・オア・エクスプレイン」という考え方です。ただしその“説明”には、論理性とストーリーが必要です。単なる言い訳ではなく、「なぜそう判断したか」「どう将来の企業価値に資するのか」を語れなければ、ステークホルダーからの信頼は得られません。
プリンシプルベースの時代に必要なのは、「何をしたか」より「なぜそうしたか」を語れる組織力です。
今回の改訂で何が変わったの?
今回の第三次改訂では、投資家との対話のあり方や、企業と投資家との相互理解の深化に向けた重要な見直しが行われました。以下は特に大きい改訂の2つのポイントです。
1. 「協働エンゲージメント」の強化
複数の投資家が連携して企業と対話を行う「協働エンゲージメント」が重視されるようになりました。これまでは1対1でのやりとりが主流でしたが、今後は“投資家連合”が企業に対して共通の課題提起を行うケースが増えると見られます。
2. 「実質株主の透明性向上」
企業は、機関投資家に対して「誰がどのくらい自社株を持っているのか」の開示を求めることができるようになりました。投資家は事前にその方針を明示し、企業もそれを理解して対話に臨むことが求められます。
単なる“開示”から“信頼形成”へ、そして個別対応から“協働”へ。これは企業価値の源泉となるコミュニケーションの質が、ますます問われる時代になったといえます。
コミュニケーション部門が押さえておくべきポイント
スチュワードシップ・コードの改訂によって、企業に求められる“対話の質”は確実に変わってきています。今やIR以外に広報、経営企画、人事、総務といった複数部門が連携して企業価値のストーリーを編み上げる必要があると考えます。以下は、特にコミュニケーション部門が意識しておきたい視点です。
◉対話は”情報提供”ではなく”価値の共創”
ある上場企業で、サステナビリティに関する方針について機関投資家から質問を受けた際、IRチームが準備していたのは単なる実績データと開示資料のみでした。これに対し、投資家側は「なぜその方針にしたのか」「将来にどんな価値をもたらすのか」といったストーリーを求めました。
投資家との対話では、“何をやったか”より“なぜやるのか”が重視されます。
◉ESGは”表面的なワード”ではなく”企業価値の中核”
「うちの会社もESGやってます」と言いながら、CSRレポートに環境活動を載せて終わっている企業も多くあります。しかし、投資家が本当に見ているのは「その取り組みが企業価値やリスクコントロールにどうつながっているか」です。
たとえば、物流業界では「災害リスクに強いサプライチェーンの整備」がESGの一部とされており、企業の実行力が評価軸になっています。サステナビリティの担当だけでなく、広報や経営企画も含めたチームで語れるようにしておくことが重要です。
◉社外取締役との連携も、対話戦略の一部
改訂コードでは、非業務執行役員(社外取締役など)との対話も価値あるものとされています。経営者だけでなく、取締役全体で一貫した姿勢を持って投資家対応に臨めるよう、社内の共有と準備が求められます。
実務への落とし込み方
ここまで紹介してきた原則や考え方を、実際に社内で機能させるにはどうすればよいのでしょうか?ポイントは「対話の質を高める仕組み化」です。以下に、現場で活用できる3つの取り組み例をご紹介します。
・シナリオベースの準備
想定外の質問にも答えられるよう、「企業価値を損なうリスク」や「中長期の成長戦略」などについてシナリオ別に準備を進めておきましょう。
・社内教育の強化
IR担当だけでなく、経営企画、広報、人事、サステナビリティ、さらには法務・総務部門にまで関係する話です。対話に関わるメンバー全員が、スチュワードシップ・コードの考え方を共有することが必要です。
・対話のプロトコル整備
未公表情報の管理、投資家への情報提供ルール、株主構成の変化への対応など、実務のガイドラインを整備することがリスクマネジメントにもつながります。
スチュワードシップ・コード改訂は、形式的なIRを脱し、企業価値を“語れる”企業だけが選ばれる時代へのシフトを意味します。
コミュニケーションは”説明”ではなく”信頼の構築”です。いま一度、社内の対話力を見直してみませんか?
参考情報:金融庁「スチュワードシップ・コード(第三次改訂版)」の確定について
スチュワードシップ・コード改訂のまとめ(FAQ)
スチュワードシップ・コードとは何ですか?
機関投資家が責任ある投資を行うための原則で、投資先企業との建設的な対話を通じて企業価値の向上と持続的成長を促す行動指針です。
2025年の改訂で大きく変わった点は何ですか?
複数の投資家が連携して企業と対話する「協働エンゲージメント」の強化と、実質株主の透明性向上が重視されました。
協働エンゲージメントのメリットは何でしょうか?
投資家連合が共通課題を提示することで、企業にとって課題の重要性が高まり、解決に向けた行動を促しやすくなります。ただし、企業側には多様な意見の整理や説明責任も求められます。
実質株主の透明性が投資家対話に重要な理由は何ですか?
誰が実際の出資者かを把握することで、投資家の意図を正しく理解でき、建設的な対話につながるからです。
企業は投資家との対話に向けてどんな準備をすべきですか?
シナリオベースでの準備、社内教育の強化、対話プロトコルの整備が必要です。単なる情報提供ではなく、企業価値を共に創る姿勢が重視されます。