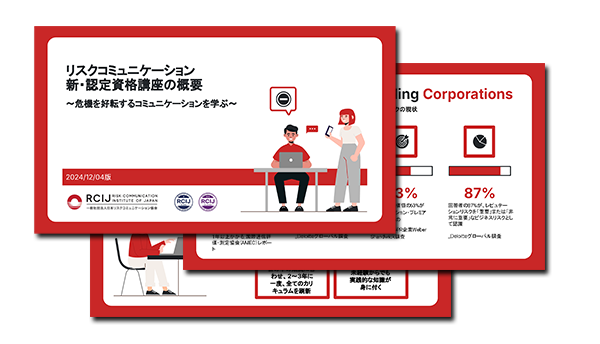コミュニケーション戦略「人権と環境」がビジネスの常識に?サプライチェーンと企業の信頼を守る4つのステップ
2025.08.04
2025年5月、日本貿易振興機構(JETRO)が「EU人権・環境デューディリジェンス法制化の最新概要」を公表しました。この中で紹介されたのが、ヨーロッパで新たに決まった企業向けのルールです。
特に注目すべきは次の2つ、
「企業持続可能性デューディリジェンス指令(CSDDD)」
「強制労働による製品を禁止する新しいルール」
これらはEU内でビジネスを行う企業だけでなく、サプライヤーや取引先として関わる日本企業にも影響を与える可能性があります。
そこでこの記事では、これらの新ルールをリスクだけでなく、信頼構築の好機と捉え、企業がどう準備すべきかを解説します。
Contents
なにが変わるの?ポイントをざっくり解説
「CSDDD(企業持続可能性デューディリジェンス指令)」では、一定規模以上の企業に対し、次のような義務が課されます。
- 自社および取引先での人権・環境リスクの特定と評価
- リスクが見つかった場合の対応(防止・軽減・改善)
- 苦情処理や情報公開の仕組みづくり
- 気候変動に対する移行計画の策定と実施
このルールは2024年7月に発効し、各国で国内法化された後、2028年から段階的に適用が始まります。
また、現在は手続きや義務内容の一部を簡素化する「オムニバス指令案」の議論も進んでおり、今後内容が変更される可能性もあります。
「強制労働製品禁止規則」とは?
こちらのルールは2024年12月に施行され、2027年12月から実際の適用が始まる予定です。
この規則では、強制労働により生産された製品のEU域内での流通や、EUから他国への輸出が禁止されます。企業の規模に関係なく、EU市場で製品を扱う全ての企業に影響があります。
たとえ自社がEUに直接輸出していなくても、自社製品がサプライチェーンを通じてEUに届いている場合、情報提供や対応を求められることがあり得ます。
情報が企業の評判を左右する時代に
SNSの力が強まる中、人権や環境問題への対応を誤ると企業は一気に信頼を失いかねません。たとえば「この製品、実は強制労働で作られていた」といった指摘が出れば、その情報が真実かどうかに関わらず、企業のブランドイメージには深刻な影響を及ぼします。
そのため、今後は“知らなかった”では済まされず、「どれだけ事前に調べて、どう対応していたか」が問われます。
しかし、こうした規制は企業にとって負担とも言えますが、逆に活かすことも可能です。
たとえば、次のような対応が「透明性」や「持続可能性」に積極的な企業としての印象を高める可能性があります。
- CO2排出の目標と進捗を社外に発信
- 高リスク地域での取引停止や監査体制の強化
- 外部の国際基準(国連指導原則やOECDガイドラインなど)に基づいた対応
情報開示の質が問われる今、信頼を得るうえでの“コミュニケーションの中身”がより重要になってきているからです。
では日本企業に求められる備えとはどんなものがあるでしょう?以下にサプライチェーンと企業の信頼を守るための4つのステップをご紹介します。
1. サプライチェーンの可視化と記録管理
○ 原材料調達や生産過程の追跡、リスクの見える化
2. 高リスク領域の把握
○ どの国や製品が人権・環境リスクを抱えやすいかを特定
3. 社内の体制整備と横断的な連携
○ 法務・調達・CSR・広報・経営企画が連携するチームづくり
4. 情報発信の準備
○ 想定問答集、FAQ、Webサイトでの開示体制の整備
5. ガイドラインや法改正動向の継続的モニタリング
○ 欧州委員会によるガイドラインや国内法の施行状況に注視
ルールへの対応は「信頼づくりの戦略」に
EUの新ルールは、企業にとって新たな義務である一方、正しく準備し、きちんと伝えれば「信頼ある企業」としての評価につながります。
“リスク”という言葉にとらわれず、自社の価値観や強みを伝える機会ととらえることも可能です。
こうした制度の変化を、戦略的コミュニケーションの一環として活用する──その発想こそが、持続可能性が重視される時代における新しい企業の生き残り戦略といえるのではないでしょうか。
参考情報
日本貿易振興機構「EU人権・環境デューディリジェンス法制化の最新概要(2025年5月)」