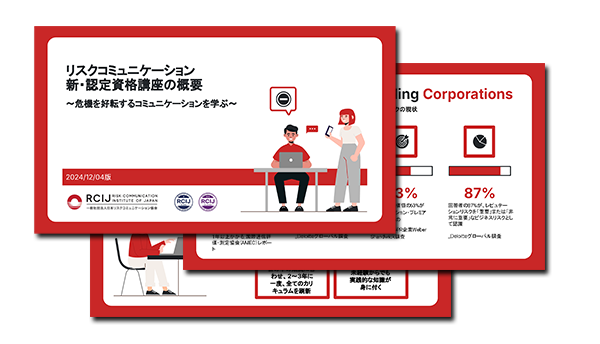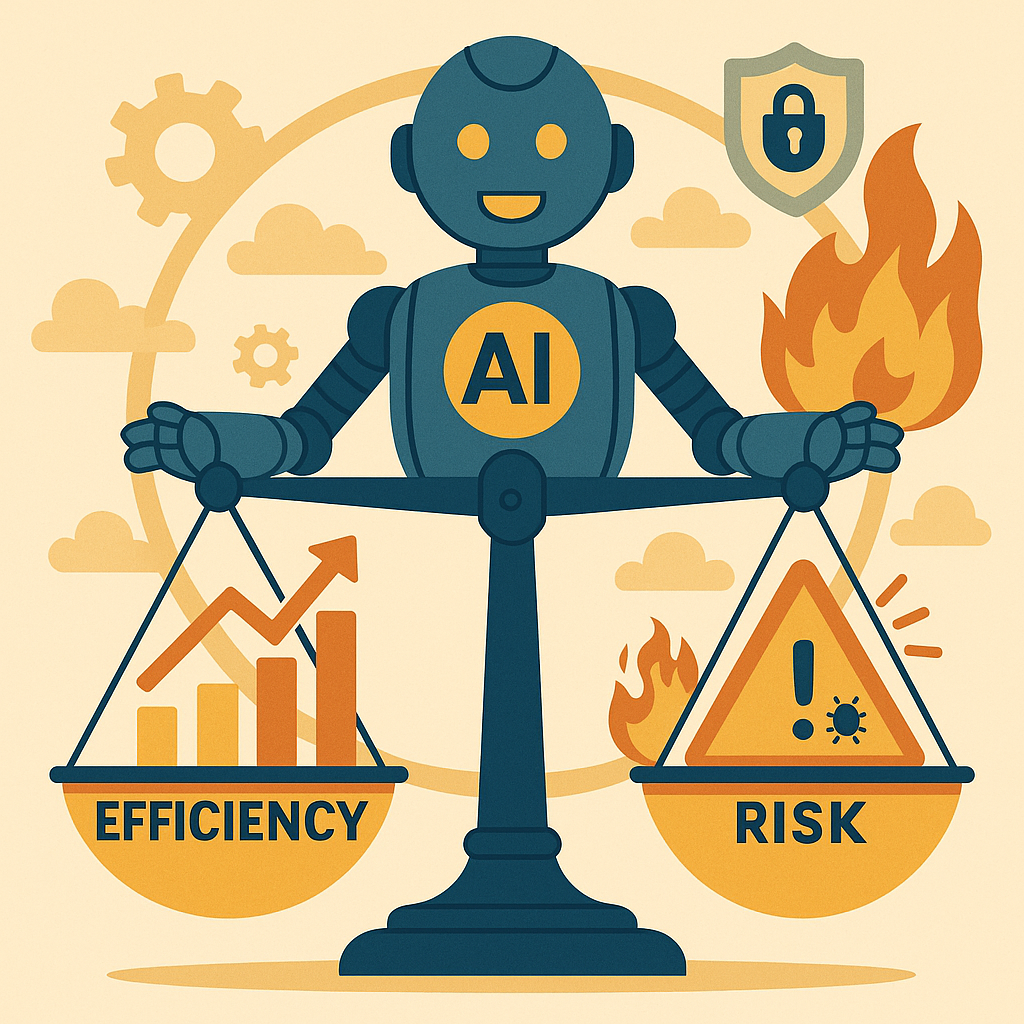
ITAIリテラシーが企業の競争力を決める――KPMG×メルボルン大学の最新研究から考える
2025.09.19
AIの進化は驚くほどのスピードで進んでいます。ChatGPTの登場からわずか数年で、生成AIは私たちの日常生活や職場に浸透しました。ところが便利さと同時に、不安もまた広がっています。
2025年4月28日に発表された「Trust, attitudes and use of artificial intelligence: A global study 2025」は、メルボルン大学とKPMGが共同で実施した世界47カ国、48,340人を対象にしたAIに対する信頼、態度、利用実態を調査した大規模研究報告書です。(調査期間は2024年11月から2025年1月まで)
本稿では、この調査をもとに「経営にとってAIをどう位置づけるべきか」を考えます。
Contents
グローバルに広がるAI利用、その実態
調査によれば、世界の人々の3分の2(66%)が、日常生活・仕事・学習でAIを意識的に使っています。特に学生の利用は高く、83%が学習に活用していると答えました。一方で、AIについての体系的な教育や研修を受けた人は4割に満たず、半数近くは「自分はAIを理解していない」と感じています。
つまり「使っているけれど理解はしていない」状態が広がっているのです。
表面的な便利さに依存する社員と、リスクを直視する経営層の間で、意識のギャップが広がりかねないアンバランスさがあると考えられます。
信頼できるのは「技術力」、不安なのは「安全性」
人々のAIへの信頼は二面性を帯びています。技術的な正確さや出力の有用性については65%が信頼を示した一方で、安全性や倫理性については52%しか「信頼できる」と答えていません。
例えば、医療分野でAIが病気の診断を助けることには期待が集まる一方、個人情報の取り扱いや誤診リスクへの懸念は根強く残っています。
この「便利さは認めるが、社会的な影響は不安」という二重構造こそ、AIガバナンスの難しさを物語っています。
先進国と新興国で分かれる“信頼格差”
さらに興味深いのは、先進国と新興国でAIに対する態度が大きく異なる点です。
- 先進国では、信頼度39%、受容度65%にとどまる
- 新興国では、信頼度57%、受容度84%に達する
この差は「AIがもたらす利益をより実感できているか」に起因します。
インドやナイジェリア、UAEでは利用率も高く、AIを経済成長の推進力として捉える姿勢が目立ちます。対して日本や欧州の一部では、規制や倫理面への不安が先立ち、「慎重な受容」が主流となっています。
経営層にとって重要なのは、この国ごとの認識の差がグローバル事業のリスクに直結するという点です。
職場でのAI:効率とリスクの同居
職場でAIを使う社員は58%。半数以上が「業務効率が上がった」と答えています。しかし同時に、AIによる判断に過度に依存し、同僚との協働や上司との対話が減っているという声も多く聞かれました。
さらに深刻なのは、社員の半数近くが「組織の規定に反して機密情報をAIに入力した」と告白している点です。セキュリティやコンプライアンス面でのリスクは見過ごせません。
この結果は、企業のAIポリシーが「利用のスピード」に追いついていない現実を示しています。
また、学生の83%がAIを学習に活用しています。効率化やストレス軽減といったメリットは大きい一方で、「批判的思考力の低下」や「自分で考える習慣の喪失」が懸念されています。
つまり、これから社会に出る世代は「AIを前提とした学び方」をしているのです。これは企業にとって、人材育成や採用基準の再設計を迫られる課題になるでしょう。
規制とガバナンス:人々の期待と現実のギャップ
70%の人が「AIには規制が必要」と答えていますが、現在の法律が十分だと考える人はわずか43%にすぎません。特に生成AIによる偽情報対策については、87%が「法規制を強化すべき」と求めています。
人々は「企業任せ」ではなく、「政府と企業の協働によるルールづくり」を強く望んでいます。経営層にとっては、ガバナンスの不備がレピュテーションリスク(評判リスク)に直結する時代になったことを意味します。
経営への示唆:AIリテラシーと信頼をどう築くか
この調査から見えてくる最大のメッセージは「AIリテラシーが組織の競争力を左右する」という点です。
社員がAIを盲目的に使えばリスクが増えます。しかし、理解し、批判的に使いこなせば生産性と信頼の両立が可能です。そのために必要なのは、単なる研修ではなく、経営トップを含めた「組織文化の変革」です。
- AIリテラシー教育を全階層で実施する
- AIの利用ポリシーを策定し、遵守を徹底する
- 規制や国際基準に沿ったガバナンスを構築する
これらはコストではなく、未来への投資だと考えるべきでしょう。
AIはすでに経営環境の前提条件になりました。
利用が加速する一方で、信頼は揺らぎ、規制は追いついていません。
この不均衡をどう埋めるかが、これからの企業の競争力を決定づけます。
今回の調査は、そのための羅針盤となるはずです。
便利さと不安、期待と不信。その狭間にある現実を直視し、経営層は次の一手を考えるときに来ています。
AIリテラシーまとめ(FAQ)
なぜAIリテラシーが企業の競争力に直結するのですか?
メルボルン大学とKPMGの国際調査では、AIを「使えても理解できていない」社員が多いことが課題と指摘されています。AIリテラシー教育が不足すると、誤用や情報漏洩のリスクが増大します。一方で、AIを正しく理解し活用できる組織は、生産性向上と信頼性を両立でき、競争力を強化できます。
先進国と新興国でAIへの信頼度が違うのはなぜですか?
調査によると、先進国のAI信頼度は39%にとどまる一方、新興国は57%と高い結果でした。新興国ではAIを経済成長の推進力として捉え、積極的に利用しているのに対し、先進国では倫理や規制への不安が先立ち「慎重な受容」が中心です。グローバル企業にとって、この信頼格差は事業展開リスクに直結します。
職場でAIを活用するメリットとリスクは?
調査では職場でAIを利用する社員の58%が「業務効率が向上した」と回答しました。一方で、機密情報を規定違反でAIに入力する社員も多く、セキュリティやコンプライアンスリスクが顕在化しています。AIの効率性とリスク管理をどう両立させるかが、企業ガバナンスの重要課題です。
生成AIに関する規制や法整備は進んでいますか?
世界的に87%の人が「生成AIの偽情報対策に法規制が必要」と答えていますが、現在の法律が十分だと考える人は43%にとどまります。規制の遅れは企業にとってレピュテーションリスクにつながりやすいため、各社は政府の動きに先行して独自のAI利用ポリシーやリスク対策を整える必要があります。
企業が今すぐ取り組むべきAIガバナンス強化策は?
- 全社員対象のAIリテラシー教育の実施
- AI利用ポリシーの策定と遵守徹底
- 機密情報の入力禁止ルールと監査体制の構築
- 国際基準や規制に準拠したAIガバナンスの導入
これらはコストではなく、将来の競争力を高める投資です。経営層を含めた組織文化の変革が、持続的成長のカギとなります。