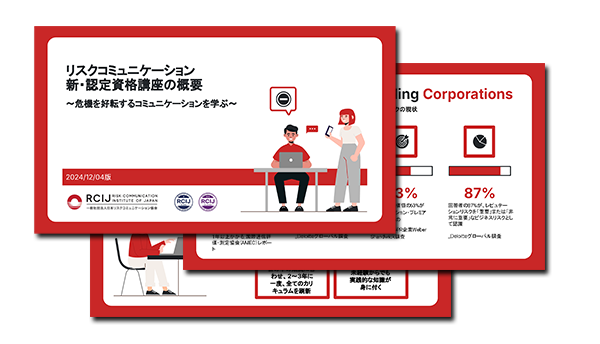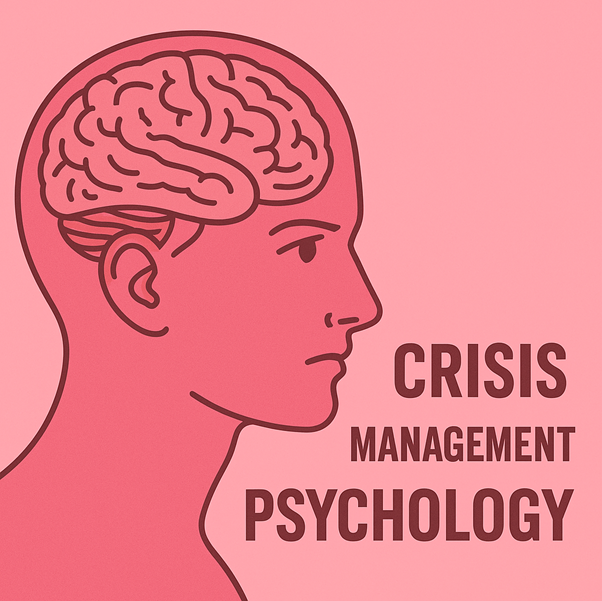
コミュニケーション戦略備えの盲点は“脳”にある──危機管理心理学が教える意思決定の落とし穴
2025.07.10
「あの会社、なんであんな対応しちゃったんだろう……」
炎上を広げる会見、火に油を注ぐSNS投稿。
そんな企業対応を目にして、思わず呆れた経験はありませんか?
企業の不祥事、SNSでの炎上、顧客対応ミス。
その多くは「人為的な判断ミス」から起きているように見えます。
でも実は、それは“判断力のある人が突然ダメになった”わけではありません。
危機に直面したとき、人間の脳は驚くほど不器用に働くのです。
そのメカニズムを解き明かしてくれるのが「危機管理心理学」。
この分野では、人が非常時に陥りやすい心の動きや脳の変化を、科学的に読み解いてきました。
本稿では、国内外の実証研究や脳科学の視点をもとに、「なぜ危機になると、判断を誤りやすくなるのか?」を紐解き、組織として備えておくべき方策を紹介します。
Contents
危機の場で、脳はどう動く?──脳科学と心理学の視点から
火災や不祥事、重大クレームなど、思いがけない出来事が発生したとき、私たちの体は自動的に”サバイバルモード”に切り替わります。
これは「闘争・逃走反応(Fight or Flight)」と呼ばれる生理的ストレス反応です。
呼吸と心拍が速まり、
脳は目の前の脅威に集中、
理性的判断をつかさどる前頭前野の働きが抑制される。
その結果、通常よりも複雑な情報処理ができなくなり、判断ミスや思考のフリーズが発生しやすくなります。
2023年に英ロンドン大学と米プリンストン大学が発表した研究(K. Mani, A. Shah, S. Mullainathan)によれば、「極度の金銭的不安」などのストレス要因があると、人間のIQが平均で13ポイント低下することがわかりました。
これは一晩の徹夜に相当するレベルです。
非常時に現れる「心理の盲点」──危機管理心理学が示す3つの罠
「うちは冷静に対処できるはず」
「うちの幹部は優秀だから」
──そう思っている組織ほど、実は見落としている“心理の落とし穴”があります。
危機管理心理学は、災害や不祥事などの非常時において、人間がどのような思考の歪みや行動パターンに陥るかを体系的に明らかにしています。
問題は、これらが無意識下で発動する点です。
どれほど冷静でロジカルな人物であっても、非常時には脳の反応が平時とはまったく異なるのです。
実際の企業危機対応で多く見られる「判断ミスの典型パターン」を、3つに分類して紹介します。
■ 集団浅慮(グループシンク)
社会心理学者アーヴィング・ジャニスが提唱した「グループシンク(Groupthink)」は、組織内で意見の一致を重視しすぎるあまり、批判的思考が失われる状態です。
実際、米国FBI教育資料「The Dangers of Groupthink」(2022年)でも、グループシンクは”最も過小評価されている経営リスク”の一つとされています。
危機下では、反対意見が「空気を読まない発言」とされやすく、沈黙や迎合が広がります。
■ 正常性バイアス
危機管理心理学で頻繁に取り上げられる概念が「正常性バイアス(Normalcy Bias)」です。
これは、人間が非日常的な出来事に直面したとき、
「たいしたことではない」
「いつも通り」
と無意識に考える心理傾向です。
米国防災庁(FEMA)の危機対応教育マニュアルでも、「避難が遅れた住民の80%以上が、正常性バイアスの影響を受けていた」と報告されています。
COVID-19の初期対応でも、日本企業の多くが「ここまで世界的に広がるとは思わなかった」と回答しています(出典:BCGグローバル経営者調査2021)。
これは典型的な正常性バイアスの実例といえます。
■ ストレスと認知機能の低下
急性ストレスが人間の認知に与える影響については、米国国立衛生研究所(NIH)やWHOが繰り返し警告しています。
2022年、米コロンビア大学の神経心理学研究グループが発表した論文では、「高ストレス下の被験者は、注意力と意思決定能力が有意に低下し、冷静な選択ができなくなる」ことが示されました。
さらに厄介なのは、当事者がその低下に気づかないことです。
危機時こそ「自分は落ち着いている」と思い込み、逆にリスクを増幅させてしまうのです。
危機に強い組織がしている「備え」
では、これらの“心理の盲点”をどう乗り越えるか?
危機管理の本質は、単に「ルールを決めておくこと」ではありません。
本当に必要なのは、“判断力が落ちる”ことを前提にした準備と、“人が冷静ではいられない”という事実に即した運用設計です。
この章では、危機に強い企業や行政機関が実践している、心理的リスクを見越した備え方をご紹介します。
単に仕組みを整えるだけでは不十分。
いかにして「脳のクセ」に合わせた対応を仕組みに落とし込めるかがカギになります。
▶ 多様な視点を尊重する文化づくり
グループシンクを避けるには、「あえて異論を歓迎する」文化が必要です。
- 異論役(Devil’s Advocate)を公式に設ける
- 意見の分かれる項目は、無記名アンケートで集約
- トップが「異論が出ないこと自体がリスク」と公言する
これらの仕組みは、実際にGoogleやNetflixなどのグローバル企業でも活用されています。
▶ 定期的な危機シミュレーション
米国では、危機対応の演習(Crisis Simulation Exercise)が企業法務やBCPの一部として制度化されています。
BCPレポート(McKinsey, 2022)によれば、「演習のある企業は、ない企業に比べて初動の正確性が3.5倍高かった」との結果が出ています。
危機管理心理学の視点では、演習の意義は「脳の回路を作っておく」ことにあります。何度か模擬的に体験しておくことで、実際の非常時にも迷わず行動できます。
▶ 判断を支えるツールと休息の設計
WHOの「心理的危機対応ハンドブック(2020)」では、ストレス下における判断力の低下に対応するため、次のようなツールが推奨されています。
- チェックリスト
- 判断基準カード
- ステップ別初動マニュアル
さらに、「決定疲れ(Decision Fatigue)」を避けるため、
- 危機時のシフト制(管理職含む)
- 意思決定の分担(すべてを1人で背負わない)
といった制度も重要です。
これらを“人間の脳の限界”に合わせて設計することが、現代の危機管理では有用と考えます。
“脳”を理解することが、最大の備えになる
私たちは、非常時に「うまくできない自分」を責めがちです。
しかし、危機管理心理学が示すように、それは“脳の自然な反応”でもあります。
だからこそ、経営者や広報担当、CSR、人事部門にとって重要なのは、「非常時にどうなるか」を先に理解しておくことです。
危機時の冷静さは、勇気や経験ではなく、準備と構造のデザインから生まれます。
RCIJでは今後も、脳科学・心理学・組織論を融合した危機対応の視点を提供していきます。
もし、あなたの組織で“人間の脳の限界”を前提としたリスクコミュニケーションを考えたいなら、ぜひ私たちのプログラムをご活用ください。
参考文献・出典:
- アマンダ・リプリー『最悪の事態に備えるには』より正常性バイアスの概念
wikipedia.orgen.wikipedia.org - Kate Kelland, Reuters, “Study finds poverty reduces brain power”(貧困状態のストレスがIQ低下を招く研究)
comreuters.com - Alok Jha, The Guardian, “Poverty saps mental capacity to deal with complex tasks”(金銭的不安による認知力低下に関する記事)
theguardian.com - ビズクロ「集団浅慮(グループシンク)とは?原因と事例、対策について」よりストレスとグループシンクの関係
chatwork.combizx.chatwork.com - Nordic Cyber Group “The Psychology of Crisis Management”より危機時における発言萎縮や準備不足に関するデータ
sencgrp.se - Healthline, “Stress Can Affect Your Ability to Think Clearly, Study Finds”(ストレスと認知機能低下に関する記事)
healthline.comcom - Wikipedia「正常性バイアス」ページより脳の情報処理の遅れに関する記述
wikipedia.org