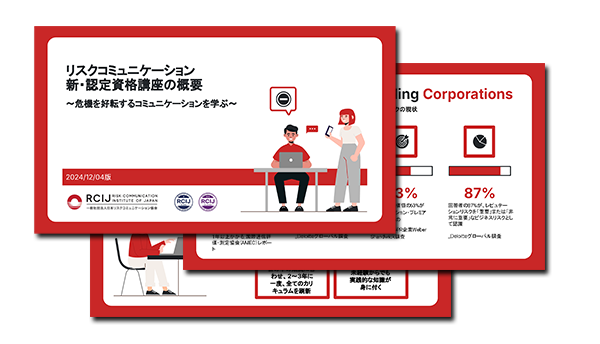ESGカスハラで辞めたのは「弱い人」じゃなくて「守られなかった人」かもしれない
2025.06.30
接客が丁寧で、応対も的確。
そんな“感じのいい人”が、ある日ふっと辞めていく。
カスタマーハラスメント──通称カスハラ。
理不尽なクレームや大声、無断撮影やSNSでの晒し行為。
耐えたところで、「頑丈なメンタル」は育たない。
傷ついたと明言しない人が、いちばん傷ついている。
組織が守るべきは、声を上げる人ではなく、声を殺している人かもしれません。
総務省が2024年に実施した最新の調査によると、地方公共団体に勤める職員の3人に1人が、カスタマーハラスメントを受けた経験があると答えています。
厚労省の調査では、顧客からの著しい迷惑行為を受けた経験がある労働者は10.8%。
医療・介護・接客・不動産・飲食のように対人頻度が高い業界では、3割~5割に跳ね上がります。
つまりカスハラは「特定の職種では、もはや日常」と言ってもいいかもしれません。
トップが言わないと、現場は言えない
「お客様には誠実に対応しよう」
もちろんそれは大事です。
しかし「すべてを聞く必要はない」 「暴言に対しては線を引いていい」 そう言ってくれる人が上にいなければ、現場では我慢を抱えることになります。
例えば和光市では、市長自らが「ハラスメント撲滅宣言」を出しています。
企業でも、「私たちは従業員を守ります」とトップが口に出して伝えないかぎり、その会社の“空気”は変わりません。
守ることを決めていない組織は、何も守れない
ルールがない組織は危うい。
しかし、ルールがあっても“運用されない組織”のほうがもっと危うい。
制度の整備とは、単なるフロー作りではなく、現場に「あなたは間違っていない」と伝えるメッセージでもあります。
従業員が“あのときの判断”をあとで振り返ったとき、 「あれでよかった」と思えるようにするには、会社がルールとして支えるほかありません。
産業医や外部のカウンセラー、匿名ツールなどを活用する余地は大きいもの。
しかし「制度はある。でも使われない」 の原因の大半は、“運用のしにくさ”にあります。
制度を機能させたいなら、「誰に、どんな気持ちで、どこで、どう伝えられるか」までを整えると良いでしょう。
スターバックスは「差別的言動には退店をお願いする」と明記しています。
企業の対応方針を事前に公開することは、従業員を守るだけでなく、 顧客にも“ルール”を共有することになります。
ルールがある場所では、信頼が育ちます。
では、どうすればいいのか?
まず、「特別な対策」よりも「当たり前の確認」から。
マニュアルが現場に届いているか、
相談先の存在が浸透しているか、
トップのメッセージが空気として残っているか
──これらを一度、見直してみましょう。
制度の整備と現場の信頼感。
その間にある“もやっとしたもの”を放置しないこと。
それが、離職を防ぐいちばんのリスク対策になります。
たとえば、栃木県宇都宮市のように、無断撮影や録音行為への具体的な対応を明示している自治体は、現場職員が安心して「線を引く」判断をしやすくなっています。
複雑な施策や高価なシステムでなくてもいいのです。
要は、従業員一人ひとりの「この判断でよかったんだろうか」という迷いに、会社がちゃんと応えているかどうか。
その答えを出せる会社が、これからの“辞められない会社”になります。
参考情報
総務省_「地方公共団体における各種ハラスメントに関する職員アンケート調査結果及び各種ハラスメント対策に関する取組事例集の公表」
厚生労働省_「職場のハラスメントに関する実態調査 結果概要(令和5年度厚生労働省委託事業)」
総務省_「地方公共団体における各種ハラスメント対策に関する取組事例集」