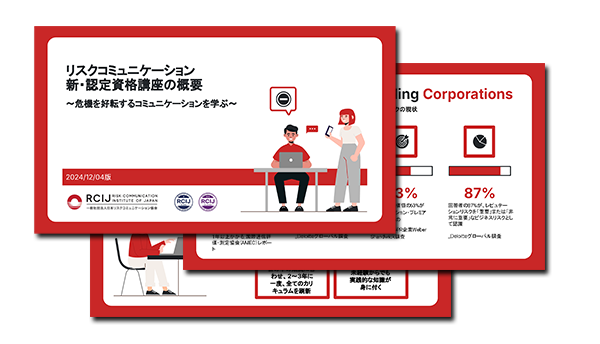コミュニケーション戦略【2025年 ASEAN地政学リスクと機会】トランプ再登板の影響と企業が今備えるべき「リスクコミュニケーション」とは
2025.04.07
【2025年 ASEAN地政学リスクと機会】トランプ再登板の影響と企業が今備えるべき「リスクコミュニケーション」とは

2025年、ASEAN地域は引き続き高い経済成長が期待される一方で、地政学的リスクがより顕在化する年になると予測されています。特にトランプ氏の米国大統領復帰による貿易政策の転換や、中国との経済対立の激化が、ASEAN各国、ひいては日本企業にとって重大な影響を与える可能性があります。
今回は、JETROが3月に公開した「ASEAN地域における2025年の地政学的展望」をもとに、企業が押さえておくべき主要なリスクと機会、そしてそれに備えるためのリスクコミュニケーションの視点について解説します。
◆ 注目すべき「7つの地政学的リスク」
地政学的リスクとは、国際情勢や政治・外交関係の変動によって、企業の経営やサプライチェーン、ブランド価値に影響を及ぼすリスクです。
とりわけ、海外展開を行う企業にとって、情勢変化に伴う情報の誤伝達・誤認識は「説明不足による信頼失墜」「レピュテーションリスク」に直結します。以下、ASEAN地域において特に注視すべき7つのリスクを整理します。
1. トランプ関税の再来
トランプ政権が再登板すれば、高率関税の発動が再び現実味を帯びます。日本企業がASEANを経由して製品を米国市場に供給している場合、その事業スキーム自体の見直しが迫られることも。影響は貿易だけでなく、金融市場の混乱にも波及する恐れがあるため、早期のモニタリング体制構築が急務です。
2. 中国製品の過剰流入とASEAN中小企業の苦境
中国の過剰生産品がASEANに流入することで、現地企業が競争力を失い、供給先としての機能不全に陥るリスクもあります。特に中小企業をサプライチェーンに組み込む日本企業は、ビジネスパートナーの経営健全性を継続的にチェックする必要があります。
3. インドネシアの保護主義強化
インドネシアでは、自国産業保護のために現地調達率の義務化や鉱物資源の輸出制限など、外資規制が進んでいます。突然の法改正や方針転換は、予告なく現地ビジネスに打撃を与えるため、「法規制の早期察知」と「対応の事前準備」が必須です。
4. データローカライゼーションとエネルギー政策
ASEAN各国では、サイバーセキュリティや主権保護の観点から「データは国内に保管せよ」という法律が進んでおり、日本本社主導のIT管理体制に制約が生じる可能性もあります。エネルギー移行に関しても、コスト・供給安定性に対する新たな不確実性が浮上しています。
5. 政治的安定性の低下
選挙による政権交代や、突発的なデモ・暴動などは、直接的な業務停止だけでなく、「その国への投資を控える」という風評被害にもつながります。広報的には、冷静な対応と継続的な説明責任が求められる場面です。
6. 南シナ海の緊張
海上輸送ルート(シーレーン)の安全性は、製造業・物流業にとって死活問題です。万一の武力衝突や航行制限に備えた「物流代替ルート」「供給遅延時の顧客対応方針」など、危機発生時の対応マニュアルの整備が重要です。
7. ミャンマーの詐欺組織と治安リスク
現地の不安定な治安状況により、社員の安全確保や物流管理が困難になっており、加えて詐欺組織の台頭により、ブランド毀損リスクが高まっています。現地パートナーとの契約管理、サイバーセキュリティ対応を強化する必要があります。
◆ ビジネスチャンスとしての「ASEAN戦略的価値」
地政学的リスクが高まる一方で、ASEAN地域は今まさに、グローバル企業にとって戦略的なビジネスチャンスの宝庫とも言えます。特に日本企業にとって、ASEANは“リスク回避先”であると同時に“成長加速のパートナー”でもあります。
1. サプライチェーン再編の受け皿としての機能強化
米中対立や台湾情勢の不安定化により、中国一極集中型のサプライチェーンからの脱却を図る動きが加速しています。この流れの中で、「チャイナ+1」戦略の重要性が再評価されており、ASEAN諸国は日本企業にとって代替・補完的な製造拠点や調達先としての地位を確立しつつあります。特にベトナム、タイ、マレーシアは、製造業や電子部品産業における信頼性の高いパートナーとして評価を得ています。
2. 日本との経済連携の深化
日本はASEANとの経済連携を国家戦略の一環として位置付けており、インフラ整備、グリーンエネルギー、デジタル化、AI・技術開発などの分野で政府と民間が連携したプロジェクトが進行中です。これにより、日本企業が進出する際の安心感が高まり、現地での社会的信頼も得やすい環境が整ってきています。
3. 新興産業の成長と誘致競争
半導体やデータセンター、原子力など、各国が国家主導で重点産業を誘致しています。特に、マレーシアの半導体産業やシンガポール・インドネシアのデジタル産業政策は、日本の技術を必要とする市場としても注目に値します。
4. ASEAN域内の経済統合の加速
不安定な外部環境を逆手に取り、ASEAN域内ではFTA(自由貿易協定)のアップグレードや、デジタル・エネルギー分野における共同プロジェクトの推進が進んでいます。これにより、域内ビジネスの効率化とコスト最適化が期待され、日本企業が複数国にまたがって事業展開する際のハードルも下がりつつあります。
◆グローバル展開における「説明責任力」の構築を
地政学的リスクは、企業活動において回避不能な「外的要因」です。しかし、リスクが顕在化したときに「どのように社内外と対話を行うか」「どのような説明がなされたか」が、企業価値を左右する決定的要因となります。
特に、ASEAN諸国に進出している日本企業は、各国ごとの政情、法制度、文化の違いに加え、グローバルな政治経済の影響も受けるという多層的リスク環境に身を置いています。そうした中で、企業が問われるのは「早期対応」と「適切な情報発信」です。
以下に企業がリスクコミュニケーション体制を強化していくうえで、特に重視すべき3つの視点をご紹介します。
① 「予兆管理」の体制構築
現地の法改正、政権交代、外交摩擦などの変化を常時モニタリングし、自社への影響度を評価する「予兆分析」の仕組みを持つことが重要です。リスクが表面化する前から、対応策と説明計画を準備することで、危機のインパクトを最小化できます。
② 「現地発信力」の強化
現地拠点のスタッフが、危機発生時にメディアや行政対応を行えるよう、危機広報研修を定期的に行うべきです。時差や言語の壁を越えて、スムーズに情報共有・発信ができる「共通フレームワーク」が求められます。
③ 「本社と現地の連携設計」
海外子会社や現地法人との間で、情報伝達や意思決定のスピードに差があると、初動ミスが起こります。誰が、いつ、どの情報を、どう共有・承認するのか。危機時の「社内対話プロトコル」の策定こそが、企業の危機管理能力を決定づけます。
ASEAN地域への展開は、成長機会と同時に高度な「リスク対話力」を企業に求めます。RCIJでは、こうした複雑な環境下でも企業が信頼を維持・強化できるよう、「地政学リスク×リスクコミュニケーション」の観点から、各種の研修・支援を提供しています。
持続可能な海外展開のために、いまこそ“説明責任力”を自社の強みに変えていきましょう。