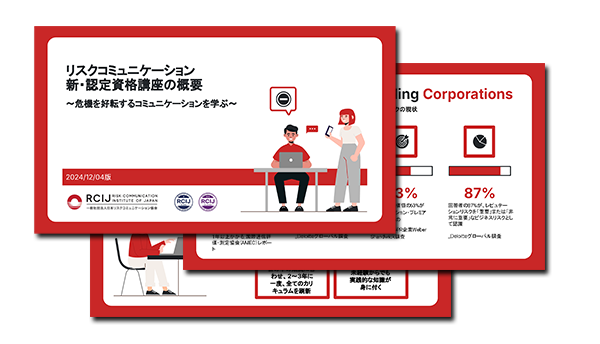IT社員の“何気ない投稿”のリスクーSNSリテラシーの再点検を
2025.05.14
社員の“何気ない投稿”のリスクーSNSリテラシーの再点検を

インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害といった「人権侵害」は、今や深刻な社会課題となっています。
2025年(令和7年)3月25日に法務省が発表した「令和6年における『人権侵犯事件』の状況について(概要)~法務省の人権擁護機関の取組~」によると、全国で新たに対応が開始された人権侵犯事件の件数は8,947件。そのうち1,707件が「インターネット上の人権侵害」に関するもので、全体の約19%を占めていました。
主な内容は、SNS等における誹謗中傷、プライバシーの侵害、差別的発言など。法務局が違法性を判断し、サイト管理者などに削除を要請した件数は628件にのぼり、削除対応率は約64%。この数字からも、ネット上の発信がいかに重大な権利侵害に直結しているかがうかがえます。
たった一言の投稿が、企業と教育機関の信用を揺るがす事例も
2025年3月、ある著名タレントの方が、X上で自身の想いを投稿しました。それに対して、ある上場企業に勤務する社員が事実に基づかない”虚偽のエピソード”を引用投稿として拡散。投稿者のプロフィールには勤務先が明記されていました。
タレントの方はその引用投稿にすぐに反応し、投稿内容が虚偽であること、自身がとったとされた行動をしていないこと、そして自身の行動が横柄だったとする印象操作への異議を唱えました。そのうえで、投稿者の勤務先の企業理念と照らし合わせて問題提起しました。
これに対し投稿者を雇用する企業は即日、公式SNSアカウントで謝罪を表明し、社内調査と処分の方針を発表しました。さらに、投稿者が教鞭をとっていた大学も契約を解除し、学長名義で謝罪文を公表する事態に発展しました。
「たった一言の投稿」が、企業の信用、教育機関の信頼、個人のキャリアにまで波及したのです。
なぜ個人のSNS投稿が企業に影響するのか?
投稿者の情報から勤務先が特定できる場合、内容そのものに問題があれば、その企業がSNSリスクを適切に管理できていないと受け止められることがあります。特に上場企業や社会的責任の大きい組織においては、情報発信に対する管理体制や倫理観が外部から注目されやすくなっています。
SNS上で投稿が拡散・炎上することで、採用活動や社外との取引関係に影響が出ることもあります。応募者が不安を感じたり、取引先が慎重な姿勢を取ったりするなど、直接的ではないものの、ブランドや信頼性に対する見えにくい損失が積み重なる可能性があります。
また、問題のある投稿が広まると、企業がそのような行為を黙認しているかのような印象を持たれることも。発信者への対応や広報の姿勢が注目され、「適切に対応しているか」が企業の信頼回復につながるポイントになります。
SNSリスクにどう向き合うか
SNSを活用した情報発信が当たり前になった今、企業として避けて通れないのが「社員による投稿リスク」。私的な投稿であっても、そこに企業名が紐づくことで、思わぬ影響を受けることがあります。では、企業はどのような準備や仕組みを整えておくべきなのでしょうか。
1.社内のルールづくりと共有
まず必要なのは、SNS利用に関するガイドラインを明文化し、全社員に対して周知徹底することです。企業名を名乗っているかどうかにかかわらず、他者を誹謗中傷したり、誤情報を拡散したりするような投稿は、最終的に企業の評判に影響する可能性があります。明確なルールがあることで、社員の判断基準が統一されます。
2.社員研修や啓発の実施
ルールを作るだけではなく、継続的な研修や啓発活動を通じて、社員のSNSリテラシーを育てていくことが重要です。新入社員研修だけでなく、中堅層や管理職も対象に含め、過去の炎上事例や対応策を具体的に共有することで、当事者意識を持ってもらうことができます。
3.トラブル発生時の初動体制の構築
SNS上のトラブルは拡散スピードが非常に速いため、初動対応が遅れると被害が拡大します。企業内では、広報・法務・人事などの担当者が連携し、必要に応じて経営層を交えて判断・対応できる体制を平時から準備しておくことが不可欠です。発生時のフローや判断基準を共有しておくことが、迅速な対応を可能にします。
おわりに
SNSは、社内広報やブランド構築にも活用できる強力なツールである一方で、適切なリテラシーと管理体制がなければ、企業にとって想定外のリスクを生む可能性があります。
特に消費者との接点が多い企業では、社員一人の投稿がブランド全体に波及するケースもあります。「問題が起きてから動く」のではなく、「何もないときにどれだけ備えているか」が、信頼の分かれ目になります。
一つひとつの発信が、誰かの目に触れ、企業の姿勢として見られている可能性があることを前提に、SNSリスクへの向き合い方を見直してみてはいかがでしょうか。